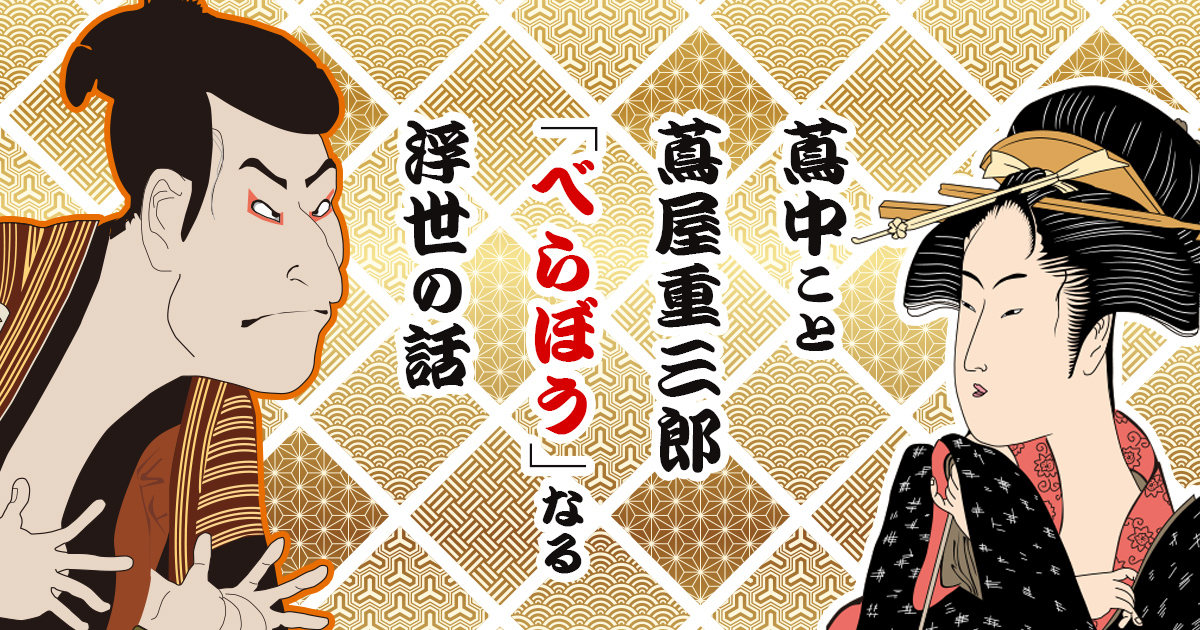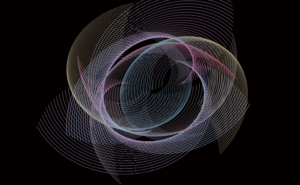この正月、昼間にBSチャンネルをザッピングしていたら「孤独のグルメ」の特番をやっていた。ふだんあまり「孤独のグルメ」は観ないのだが、しばらくチャンネルを止めて眺めていた。
例によって松重さん演じる井之頭五郎が食事をしている。彼の心の声が松重さんのナレーションで流れる。
そんな中「なんだこれ、べらぼうに美味い」というセリフがあった。
「べらぼう」って言葉、口にしてるのをちょっと久しぶりに聞いた。
「べらぼう」ってそもそも何?
今年2025年の大河ドラマのタイトルがまさにその「べらぼう」。
江戸の出版王、蔦屋重三郎の物語だ。彼の型破りな人物像を「べらぼう」という言葉にのせたのだろう。
「べらぼう」
これって江戸言葉なのだろうか? 関西ではあまり使わない?? それは知らないけれど、ともかく最近「べらぼうな金額」とか「べらぼうに大きい」など、会話の中であまりこの言葉を耳にしなくなってきた。。
べらぼう:あまりにひどいさま。はなはだしいさま。転じて人をののしるときに使う言葉。バカ。
日本語はときとして他人をののしる言葉を称賛の言葉として用いる傾向がある。
「べらぼうに美味い」も今風で言うなら「バカ美味い!」とか「クソ美味い」といった感じだ(笑)
ところでそもそも「べらぼう」ってなんだ?
ということで、ちょっとネットで検索してみた。
するとその語源は、べら=ヘラ(箆)ぼう=棒、つまりもともとは「箆棒」のことで、これは穀物を磨り潰す道具からきているという。
穀物を潰す→穀潰し(ごくつぶし)というわけである。
この馬鹿者という意味合いが、やがてひどいさま、はなはだしいさまとしても使われるようになったものと推察できる。
ところが、さらに調べると語源にはもうひとつ全くちがう説も出てきた。
「べらぼう」は「便乱坊」と書き、これは見世物小屋で人気者だった道化役の便乱坊という芸人が由来だというのだ。
「その容貌きわめて醜く、全身真っ黒で、頭は鋭くとがり、眼は赤くて円く、あごは猿のようで、愚鈍なしぐさを見せて観客の笑いを誘った」という記述もあるという。
その常識外な様子から、ひどいさま、はなはだしいさま、バカげたことの例えとなった、ということのようだ。
どちらの説が正しいのか、そこまで突っ込んで調べてはいないが、ともかく言葉の語源を調べるのもなかなか面白いものだ。
ちなみに「べらんめい」とは「べらぼうめ!」が変化したもので、これも江戸言葉で「この馬鹿野郎め」って意味だが、ののしりながら口は悪くても、なんとなく相手への親しみというか愛のようなものもちょっと感じたりする。
さらに「あたりまえだよ」を意味する「あたぼうよ!」(これも最近言う人いないかw)は「あたりめいだ、べらぼうめ!」が略された言い方。
長い言葉を略すのは今も昔も変わらないようだ。
江戸のメディア王「蔦屋重三郎」
そんなべらぼう男、江戸のメディア王「蔦屋重三郎」の波乱万丈の生涯を描く今年の大河ドラマ。日本の出版文化を庶民文化に一気に広めた立役者とも言える人物の物語なので、なかなか興味深い。
蔦屋重三郎は江戸の中期に吉原に生まれ、はじめは吉原の女郎を相手に貸本屋を営んでいたが、やがて「吉原細見」という吉原のガイドブック(これはどの店にどんな子がいて、値段はいくらくらいか、などをまとめた、まるで今の風俗店案内みたいな本w)の編集に関わるようになり、やがて「吉原細見」の発行そのものお手掛ける版元となって、そこを足ががかりにさらにビジネスを拡大、浮世絵や洒落本、黄表紙本といった娯楽の本を次々と世に出してゆく。
浮世絵では、喜多川歌麿や謎の絵師、東洲斎写楽らを世に送り、滝沢馬琴や十返舎一九といった作家(戯作者)らと親交を深めながら、黄表紙や洒落本を出版し、大ヒットを飛ばしていった。
あのTSUTAYAとの意外な関係
蔦屋重三郎の名から、やはり気になるのが今の蔦屋(TSUTAYA)の関係だが。。
結論から言うと、全く関係ない。
蔦屋の会長増田宗昭氏によると、彼の祖父が副業で営んでいた置屋の屋号が「蔦屋」だったという。そこで書店を開業するにあたり、当時の書店には「〇〇屋書店」という屋号が多かったことから、この屋号をもらって蔦屋書店としたそうだ。
蛇足だが、紀伊国屋書店も紀伊国屋分左衛門とは無関係だ。
江戸に浮世絵の一大ブームを巻き起こした蔦重。今年は浮世絵への関心が高まりそうだ。
藤沢市にある「藤沢浮世絵館」ではさっそく蔦屋重三郎の特集展示を行っている。
興味ある方はぜひ足を延ばしてほしい。
藤澤浮世絵館展示「藤沢と江戸の出版事情~蔦屋重三郎と絵師たち~」
https://fujisawa-ukiyoekan.net/f/home/