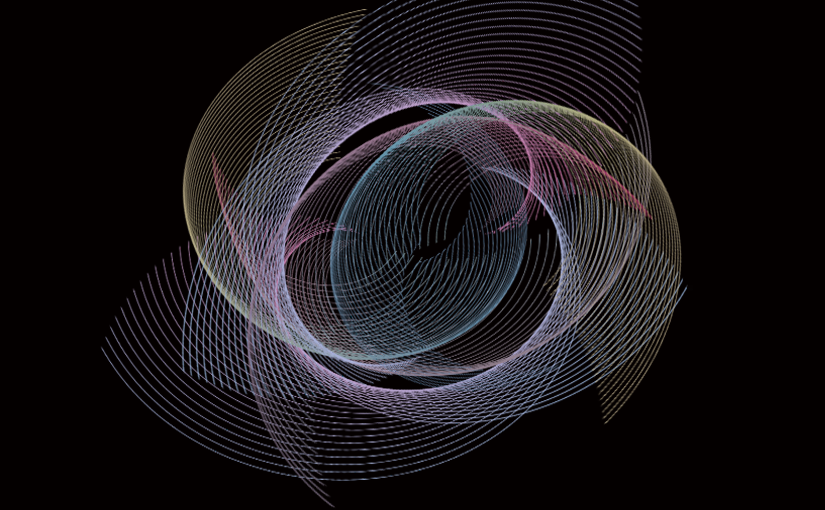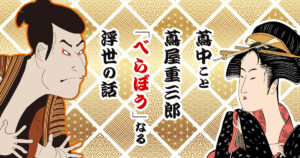デジタルアート作家の川村氏にインタビューする機会があったのだが、そもそも、が気になった。「デジタル」ってどういう意味なのだろう。気がついたらするっと身近にいた言葉。いつからこの言葉はあったのだろう。
digitalの語源はラテン語の digitusで「指で数える」という意味らしい。
英語辞書(30年以上前の筆者の高校時代のものだが)でdigitalを調べてみると一番最初に記載されていたのは「指(状)の」や「指のある」という意味であった。広辞苑には「データを数字列として表現すること」と記載されているのだが、1938年以降にパソコンが現れてから生まれた意味なのだそうだ。コンピュータが0と1のみで数値を表す2進数だからということらしい。
では、デジタルアートのはじまりはいつなのかというと、こちらもコンピューターが出始めた当初の1940年代。最初はコンピュータの情報を記録用のパンチテープやデータカードでコラージュを作ったり、打ち出された文字の濃淡を利用してアートにしていたのだそうだ。
1952年にアメリカの数学者・芸術家であるベン・F・ラポスキーがブラウン管とアナログコンピューターを使った「Oscillon No4」というアートを発表。これはアートというよりパターンといったほうがいい作品である。
また、イギリスのデスモンド・ポール・ヘンリーは第二次世界大戦中に使用された爆撃照準器を改造しコンピュータグラフィックの先駆けともいえる「ヘンリー・ドローイング・マシン」を完成させている。
1967年には、ベル電話研究所のマイケル・ノルが、コンピューターにモンドリアンの絵画《線のコンポジション》(1917年)に含まれる要素の座標を覚えさせてパターンを描いた。「線をもつコンピュータ・コンポジション」というタイトルを付け原作と比較したという。
また、1963年にアメリカMIT博士課程の大学生だったイヴァン・E・サザーランドは計算機で生成した線図形を表示するスケッチパッドシステムを考案した。その後ユタ大学でCGクラスを設立し、マウスでウインドウを操作するパソコンの画面操作法を考案したアラン・ケイなどを輩出、ここからがCG発展していく。その後カラーPCが登場しCGで色を付けることになり飛躍的に画像生成ができるようになっていった。
日本では、1963年に川野洋一氏がアルゴリズムで画像を作成した。これが日本で最初のCGである。その後出原栄一がラインドローイングで樹木の成長モデルを描き、フラクタル的(1)な画像を作り上げた。
1973年には東京・銀座ソニービルで「国際コンピューター・アート」展が催されている。
デジタルアートは広義であり、その種類や発展はさまざまであるが、コンピュータ技術の発展とともに進化し広がり続けている。これからどんな新しいアートが生まれてくるのかが楽しみである。
(1)フラクタルとは「小さな部分が全体と同じような形をしているもの」(自己相似性)のことであり、抽象的な数学の概念である
参考:美術手帳 https://bijutsutecho.com/artwiki/123
広辞苑 第7版 岩波書店 2023年
新英和辞典 研究社 1989年
情報管理 vol55 2013年 国立研究開発法人
科学技術振興機 773頁