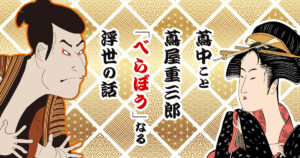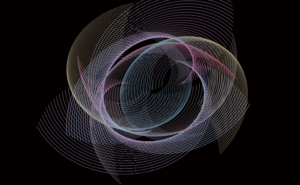かつて学研が発行した「レコードジャケットコレクション Best500」という、本がある。
私が子供のころ、母が学研で事務職としてパートに出ていた頃、たまに学研の本をもらって来ていて、その中にこの本があった。当時まだ音楽なんて全く興味のない中学生になったばかりの少年だったが、この本はなんとなく気に入って見ていた。
少々大人になり、音楽やアートにも多少の知識が付き始め、あらためてこの本を見たとき、レコードジャケットがアートの宝庫であることにあらためて気づかされた。
アートとしてのレコードジャケットの話をすると際限はないが、ここではひとまず名画が使用されたジャケットについて少々触れてみようと思う。
クラシックの世界で使用されている例は多いが、ジャズやポピュラー音楽でもその例は少なくない。
ちょっとクセ強なジャズピアニストのセロニアス・モンク。彼のアルバム「Misterioso」のジャケットにはあのデ・キリコの「預言者」が用いられてる。残念ながらなぜこの絵が使われたのか筆者の知るところではないが、直感的にはモンクのピアノとキリコの絵という組み合わせは腑に落ちる。またモンクの作品では「Plays Duke Ellington」というデューク・エリントンの有名曲を演奏したアルバムで、ルソーの「ライオンの食事」がジャケットに起用されている。
名画とは話が離れるが、ジャズにおけるジャケットアートといえば、デヴィッド・ストーン・マーチンというイラストレーターを外せない。
有名なのはビリー・ホリデイの「Billie Holiday at Jazz at the Philharmonic」というライブアルバムのジャケット。
ベッドに裸の女性が泣き崩れるような姿。そして電話の受話器。想像を掻き立てる。
ジャズのジャケットは彼の作品のオンパレードです。太さの不安定でかすれたような線で描かれるドローイング。この線は「DSMライン」と呼ばれ、のちにあのアンディ・ウォーホルのブロテッド・ラインを使った作品に多大な影響を与えた。そのウォーホルの作品もその後多くのレコードジャケットに起用されている。あの山藤章二氏も影響を受けたと言ってるそうで、なるほどあのタッチうなずける。
マーチンの手がけたジャケットをコレクションして、壁一面に飾ったら、超クールだななどと妄想してしまう。
名画に話をもどす。ソニーロリンズのアルバム「Falling In Love With Jazz」ではアンリ・マチスが晩年取り組んだあの切り絵の作品の一つ「ハート」が起用されています。ま、タイトルが「恋に恋して」をもじった「ジャスに恋して」なのでこうなったのでしょうか?
ジャズの話ばかりになってしまったのでちょっと毛色を変えて、シャンソンのお話。僕が敬愛して止まない画家ロートレック。
彼の最も印象的な作品が、歌手アリスティード・ブリュアンのポスター。あの黒いコートに真っ赤なマフラーは一度見たら忘れられない。パリで歌手・女優として活躍したパタシューことアンリエット・ラゴンは、このブリュアンの曲を歌ったアルバムで、自身の顔の背後に大きくロートレックのブリュアンが配されている。うーん正直パタシューの顔が邪魔。
またシャンソンのオムニバスアルバム「Chansons 1900」には娼婦「ジャヌ・アヴリル」が起用されている。あの片足を上げた構図のインパクトは効果絶大だ。
とにかくレコードジャケットとアートという話、すでに膨大なテキストが世の中にあり、今更僕なんぞがちょろっと書ける話でもないことは百も承知だが、それでもたまたまこの記事を目にした人にとって、これが入口となれば幸いだ。
興味があればいろいろ調べるといい。ジャケットの楽しみ方もまた変わるだろう。