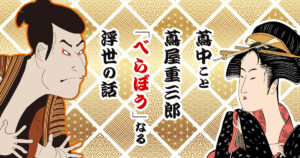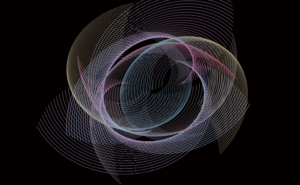かつて北海道でolive少女だったわたしは原宿や下北沢に憧れていた。ふりふりふわふわの服をきたおしゃれな女の子たち。ラフォーレ原宿やファーマーズテーブルに行きたかった。
買い物につかれてクレープをほおばりたかった。原宿は憧れの街だった。
だが・・・実は「原宿」はない。
正確にいうと原宿という地名がないのだ。
原宿の地名の由来は江戸時代以前の鎌倉街道の宿駅だ。かつてこの一帯が千駄ヶ原(せんだがはら)と呼ばれる原っぱであり、原宿の「原」はそこに由来しているそうだ。
原っぱの中にある宿場町だから「原」「宿」なのだろうか。
鎌倉街道とは幕府があった鎌倉と各地を結ぶ街道のことだ。原宿には鎌倉と奥州(東北地方)を結ぶ街道が通っており、重要な宿駅であった。宿駅は街道沿いで、旅人を泊めたり、荷物を運ぶための人や馬を休ませる宿場のことであり、江戸時代になると宿場町とも呼ばれるようになる。江戸時代にはこの一帯は「原宿村」とよばれていた。
1889(明治22)年に市町村制が施行されると、千駄ヶ谷・原宿・穏田の3村で千駄ヶ谷村となり、さらに、昭和7年10月1日には渋谷町、千駄ヶ谷町、代々幡町が合併し、東京市渋谷区が誕生した。(東京都ではなく東京市!)
その当時でもまだ原宿は原宿1丁目から3丁目まであったのだが、1965年(昭和40年)に住居表示に関する法律に基づいて廃止され、町名は「神宮前(じんぐうまえ)」に統一された。
では、なぜ神宮前なのか・・・・
原宿と一緒に合併した穏田という地名と原宿をまとめようとしたのだが、どっちの名前を存続させるかが決着つかなかった。ならば、明治神宮の前だし、ということで、神宮前という新しい地名がつけられてしまったのだ。もちろんわかりやすい街づくりは大事だが、由緒ある地名がなくなるのはもったいない気がする。
よもやまばなしのついでにもう一つ。原宿と合併した穏田についてだ。穏田という地名の由来は、400年近く前にさかのぼる。徳川家康は信頼していた伊賀忍者の一族郎党を、この辺りに住まわせた。 忍者の隠れ里ということで隠田と呼ばれるようになったという。それがいつのころからか「穏田」という字を使うようになったようだ。
隠田にある穏田神社について神社庁のホームページには
天正十九年伊賀衆が穏田の地を家康より賜り給地となる。以後この辺開け江戸時代は第六天社と称し明治維新の際に穏田神社と改称す。ご祭神は美容、技芸上達、縁結びの神として尊崇される。
と記載されている。伊賀衆とは伊賀忍者のことだ。原宿に忍者がいたとはなんだかイメージがわかない。ちなみにこのことを意識してか原宿竹下通りには「忍者カフェ」があるそうだ。
忍者カフェは、お子様を中心に「忍者になって遊べちゃう遊び場」をテーマにした、日本初の忍者屋敷風のエンタメカフェとのこと。大人も楽しめるそうなのでぜひ体験してみたらいかがだろう。
忍者体験カフェ原宿(ニンジャタイケンカフェハラジュク)