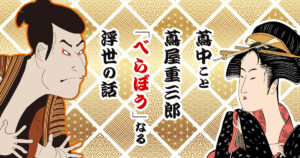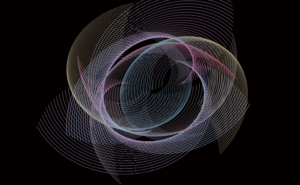両国駅を降りると、目の前にそびえる国技館。通りには力士の姿が行き交い、街全体に相撲の空気が漂う。駅構内には往年の名力士の写真が並び、ここが「相撲の街」であることを実感する。

両国という地名は、江戸初期に隅田川に架けられた両国橋が由来だという。当時の日本は今の「県」ではなく「国(くに)」という区分だった。隅田川の西は江戸城や武家屋敷が集中した江戸の中心・武蔵国、東は農村や町場も多い下総国。つまりこの橋は「二つの国を結ぶ橋」だったのだ。
江戸の発展とともに下総の一部が武蔵に編成替えされ、国は渡らなくなったが呼び名は両国橋のままである。

この橋ができるまで、対岸に渡るまでは渡し舟しかなかった。隅田川は実質的な国境であるため、幕府は防衛上の理由から隅田川への架橋を認めていなかったのだ。
しかし、明暦3年1657年、江戸の三大大火ともいわれる(めいれきのたいか)がおこる。その被害は延焼面積・死者ともに江戸時代最大だったという。
「ローマ大火(古代ローマ)」「ロンドン大火(イギリス)」と並び世界の三大大火として挙げられることが多いといえばその被害の大きさがわかるだろうか。
江戸の都市部の6割以上が消失、橋がないために逃げ場もなく、死者は3~7万人にも及んだ。
明暦の大火
明暦の大火は別名「振袖火事」とも言われている。
明暦3年、西暦1657年の1月18日。浅草諏訪町の大増屋の娘・おきくは花見で見かけた美しい青年に一目ぼれの末、恋煩いで死亡。大増屋は彼女の振袖を棺桶に掛けて本妙寺に葬る。しかし葬ったはずのその振袖は古着屋を介し別の娘に渡るが翌年に死亡。さらにこの振袖は再度古着屋を介し別の娘の元に渡るが、この娘もその翌年に死亡。さすがになにかあると本妙寺で供養しようと燃やして読経していると火のついた振袖は舞い上がり寺に燃え移りそこから大火事になったという。 「振袖火事」の逸話は後世の創作とも言われるが、人々の記憶に焼きつくほど、この火事は江戸の街を壊滅させた。
この大惨事の反省を受けて幕府は防災を重視した町づくりを始める。避難経路確保と同時に隅田川の東側(本所・深川)まで町を広げ人口分散をはかった。橋の建設は必須であった。

橋がかけられると、西側の川沿いには火除けのための広小路が設けられる。芝居小屋、寄席、茶屋、舟宿(屋形船を出す店)が軒を連ね、、江戸三大広小路のひとつとして上野、浅草と並び賑わった。
橋の東側は「向両国(むこうりょうごく)」と呼ばれ、広小路にあふれた人々を当て込んで発展した。こちらは、見世物小屋(軽業、珍獣、ろくろ首、からくりなど)、 屋台、露店などがずらりと並び、広小路に比べると雑多な賑わいだったようだ。一見同じようだが、広小路が幕府公認の遊び場なら向両国は庶民の熱気が生んだちょっと猥雑な盛り場といったところだろうか。両国一帯は繁華街として発展していった。

向両国の回向院では勧進相撲が行われた。勧進相撲とは寺院や神社の建立・修繕、公共事業などの費用を集めるための相撲興行のことだ。回向院は、明暦の大火で亡くなった身元や身寄りのわからない人々を弔うために当時の将軍家綱の命で建てられたお寺である。各地で行われていた春秋二回の興行は回向院が定位置となり、明治42年旧両国国技館が完成するまでの76年間、小屋掛け回向院相撲が続いた。
実は回向院には鼠小僧次郎吉の墓がある。黒装束にほっかむり姿で大名屋敷から千両箱を盗み、町民の長屋に小判をそっと置いて立ち去ったというのは有名な話。長年捕まらなかったことから、その強運にあやかろうと、墓石を削り、金運アップや合格祈願のおまもりとして持ち帰る風習があるとのこと。立ち寄ってみてはいかが?ちなみに鼠小僧の墓の隣は猫塚だという・・・
いまでは両国橋界隈は当時の賑わいとは変わり落ち着いた街となり、すっかり相撲の聖地である。しかしあちらこちらに江戸の名残が残っている。(駅の浮世絵の写真も)両国橋を渡りながら、江戸の息づかいを感じてみてはいかがだろう。